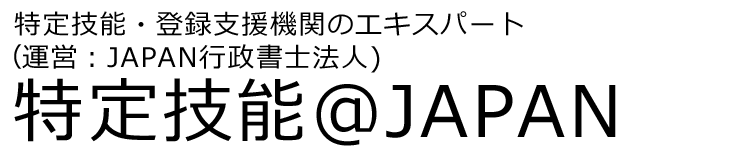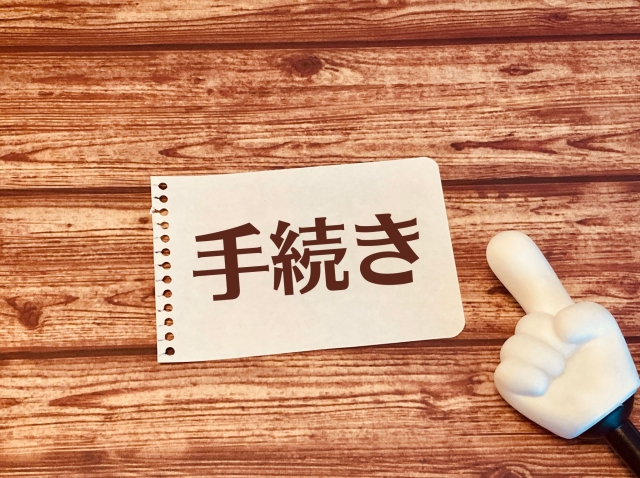2025年4月1日「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」の改正に伴い、届出の取扱い及び参考様式が一部変更となりました。届け出の頻度や内容等が変わり、所属機関や登録支援機関の関係者にとっては大きな関心事であるといえます。
定期届け出が年に一回に
今までは3ヶ月に1回、つまり年に1年に4回の届出が義務化されていた定期届出ですが、改正後は1年に1回の届出で足りることとなりました。対象年度は4月1~から3月1日となり、その期間の受入れ・活動・支援実施状況の届出を翌年度の4月1日から5月31日までに提出する必要があります。定期届出の頻度は減ったものの、随時届出や定期面談は今まで通り行う必要がある点には注意が必要です。
定期面談の「オンライン」での実施が可能に
これまで対面により直接話をすることとしていた定期面談について、下記の条件下においてオンライン面談の実施が可能となりました。
・オンライン面談の実施について面談対象者の同意があること
→ 特定技能外国人の同意の確認については、支援計画書において行う
→ 特定技能外国人の監督をする立場にある者については、任意の様式で同意の確認
※面談対象者の同意がない場合や、(過去に同意をしていても)面談対象者が対面による面談を希望した場合は、対面による面談を実施する必要がある
・オンライン面談の様子を録画して、一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年以上)保管
→地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応じる必要がある
・オンライン面談を実施する場合、周囲に面談対象者以外の者がおらず、面談対象者が第三者の影響を受けずに発言していることを確認
→開始前に面談対象者に部屋全体を映してもらい、周囲に人がいないことを確認
→開始前に面談対象者がイヤホン等を装着していないこと、別のモニターやマイクが ないことを確認
→面談対象者には、正面(カメラ)を向いて話すよう依頼
→面談時に毎回同じ質問を繰り返すのではなく、質問の順番を変える、質問の仕方をえるなどして面談対象者の様子を確認
※オンライン面談の結果、1号特定技能外国人の業務内容、待遇及び保護に関する事項において問題があることが疑われる場合や第三者による面談への介入が疑われる場合には、改めて対面による面談を行う必要がある
以上の条件のもとオンラインでの実施が可能となりましたが、円滑な支援の実施のためには面談対象者との信頼関係を構築する必要があることから、受入れ後初めての面談及び面談担当者変更後の初めての面談については、対面による面談を実施することが望ましいとされています。また必須ではありませんが、1年に1回以上は対面による面談を実施することが望まれています。
特定技能外国人の受入れ困難時の届出
自己都合退職の申出があった場合の取扱い
自己都合退職の申出が特定技能外国人側からあった場合については、受入れ困難の事由とはせず、当該申出があった時点での届出の提出は不要とします。ただし、その後、当該外国人が退職した場合には、従前のとおり「雇用契約終了の届出」を提出する必要があります。
1か月以上「特定技能」に基づく活動ができない場合
「特定技能」の許可後、受入れ機関において「特定技能」としての活動ができない場合には、受入れ困難に係る届出を提出する必要があります。 なお、特定技能外国人が雇用後に1か月以上活動ができない事情が生じた場合だけではなく、特定技能外国人が許可を受けた後に1か月経過しても就労を開始できない場合についても届出を提出する必要があります。この点に関し、1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書及び行方不明が判明した際の状況説明書の参考様式が追加されました(参考様式第3-4号)。
特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出(新設)
現行の「出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出」は廃止となり、「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出」に変更されました。
想定される届出事由は、主に、
・ 税金や社会保険料等の滞納が発生したとき(第2条第1項第1号不適合)
・ 特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき(第2条第1項第2号不適合)
・ 関係法律による刑罰を受けたとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 実習認定の取消しを受けたとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)
などが想定されます。
機関の適格性に関する書類
令和7年3月31日までに受入れを開始している機関
入管法施行規則の改正に伴い、既に受入れを開始している機関の適格性(所属機関が特定技能外国人を適切に受け入れることのできる企業か否かの要件)については、1年に1度提出する定期届出「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出」(以下「定期届出」という)において確認することになります。
令和7年4月1日以降に初めて特定技能外国人の受入れを開始する機関
令和7年4月1日以降に初めて特定技能外国人の受入れを開始する場合は、当該在留諸申請において、特定技能所属機関の適格性に関する書類を提出する必要があります。在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行い、かつ一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる次に掲げる機関等については、適格性に関する書類の提出を省略することが可能です。
●対象となる機関
過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行い、かつ以下のいずれかに該当する機関
※ 令和8年4月1日以降に提出する定期届出において、提出書類の省略をするためには、オンライン申請及び電子届出を行うことが提出書類の省略を認める必須要件となりますので、定期届出において書類の省略を希望する場合には、オンライン申請及び電子届出の利用者登録を行う必要があります。
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
④ 一定の条件を満たす企業等
⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
⑥ 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債 務超過となっていない法人
なお、提出を省略する場合であっても、必要に応じて地方出入国在留管理局から提出を求められた場合は提出する必要があります。
まとめ
今回の改正により、届出の頻度や内容、面談の方法に柔軟性が生まれる一方で、手続上の注意点や新たな義務も追加されています。登録支援機関や所属機関の皆さまにとっては、制度改正の背景を正しく理解し、変更点に確実に対応していくことが求められます。
「知らなかった」では済まされない制度運用の現場において、最新情報の把握と社内体制の見直しは不可欠でしょう。
JAPAN行政書士法人では、特定技能制度に精通した専門家が、各機関の状況に合わせた実務対応をサポートしています。届出内容の確認や面談体制の整備、適格性書類の省略に関する対応など、お困りの点があればお気軽にご相談ください。