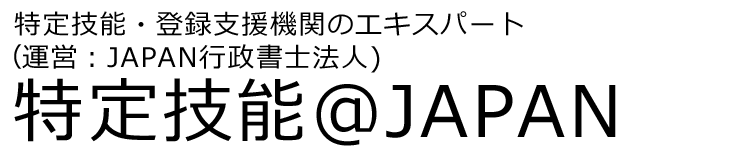現在登録支援機関になるためには支援責任者及び支援担当者の設置が必須となっていますが、この支援責任者及び支援担当者に関して、要件が厳格化される法改正が予定されており(2027年4月1日予定)、本稿ではそれらを重点的に解説させていただきます。
登録支援機関になるための要件(現行制度)
以下のイ~ニは、登録支援機関として登録を受けるために必要となる要件になります。
イ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
ロ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること
ハ 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
ニ イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること
登録支援機関になるための要件としてイ~ニがありますが、ロやニで申請するのはハードルがとても高く、ほとんどの場合でイかハによって要件を満たすこととなりますので、この2つに絞って説明いたします。
まず、イによって要件を満たすためには、「過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績」が求められるところ、2年以内に中長期在留者(例:「技術・人文知識・国際業務」)を雇入れさえすれば良く、比較的満たしやすい要件といえます。またこの点に関し、「登録支援機関になろうとする者」が満せば良く、支援責任者など、所属する職員に求められる要件ではありません。
次に、ハによって要件を満たすためには、「支援責任者となる者」が「過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験」が求められます。相談内容や件数は限定されませんが、業務として行われたこと(報酬や対価を伴う必要がある。)が求められるためボランティアなどで行った経験は含まれないため注意が必要です。また重ねてとなりますが、イとは違い登録支援機関になろうとする者自身ではなく、「支援責任者となる者」が求められる要件となります。
※イ・ハ共通して、留学生や身分系ビザ(永住者や定住者)などの就労系以外の在留資格を有する外国人は対象外となる点に注意が必要。
「支援責任者」とは(現行制度)
「支援責任者」とは、登録支援機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。現在の運用において、支援責任者は必ずしも常勤である必要はありません。しかし一方で、支援責任者は登録支援機関になろうとする機関に所属していなければならず、業務委託などでの就任は明確に禁止されています。
「支援担当者」とは(現行制度)
「支援担当者」とは、登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望まれます(必須ではありません。)。また支援責任者とは異なり、登録支援機関の「支援業務を行う各事務所に所属する者の中」から、少なくとも1名以上の支援担当者を選任する必要があります。
2027年4月施行予定の加重要件
支援担当者及び支援責任者につき、以下の通り要件が加重され、厳格化されることとなりました。
支援責任者
支援責任者に関し加重された要件を、改正の前後で比較していきます。
今までは、「登録支援機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)の中から選任」という記載がされていましたが、改正後は、「支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役職員の中から支援責任者(過去3年以内に法務大臣が告示で定める講習を修了した者に限る。)を1名以上選任」という記載に変わり、以下の通りいくつかの文言が加筆されていることがわかります。
- 支援業務を行う事務所ごとに
→支援業務を行う事務所が複数ある場合、法人全体で1人では足りなくなった
- 常勤の役職員の中から
→非常勤の支援責任者が認められなくなった
- 過去3年以内に法務大臣が告示で定める講習を修了した者
→一定期間内に講習を修了した者しか支援責任者になることができなくなった
今までは名ばかりの支援責任者も多く存在し、登録支援機関としての要件を満たすためだけに支援責任者として就任する、といった事例も多くありました。しかしこの改正によって支援責任者が常勤であることが必須となり、支援責任者として要件を満たしているものが籍だけ置き、実際には業務に関与しないという方法が事実上不可能となりました。今後登録支援機関の登録をしようとしている方だけでなく、現在もそのような方法で登録支援機関として活動している方は注意が必要です。
支援担当者
支援担当者に関し加重された要件を、改正の前後で比較していきます。
今までは、「登録支援機関の役員又は職員であり、支援業務を行う事務所に所属する者の中から、少なくとも1名以上の支援担当者を選任」という記載がされていましたが、以下の3つの要件が加重されました。
- 支援担当者(支援責任者が兼ねること ができる。)の数が、当該支援業務に係る特定技能外国人の数を50で除して得た数を超えていること。
→支援担当者1人につき、50人以下の特定技能外国人しか支援することができなくなった
- 支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)の数が、当該支援業務に係る特定技能所属機関の数を10で除して得た数を超えていること。
→支援担当者1人につき、10以下の所属機関しか支援することができなくなった
- 常勤の役職員の中から選任していること。
→非常勤の支援担当者が認められなくなった
支援担当者に関しては、常勤であることを求めることに加え、今までは支援を行う事業所ごとに1人選任するだけで良かったものが、支援担当者1人当たりの支援可能な特定技能外国人の数や所属機関の数が制限されることとなりました。これは支援業務を行うことができる者を支援責任者や支援担当者に限ったうえで、支援担当者が現実的に対応可能な範囲でしか支援業務を行うことができない旨定めたものとなります。
まとめ
ここまで、改正後(令和9年4月1日予定)の加重要件を解説してきましたが、登録支援機関として業務を行っていくうえで非常に大きな改正が行われる見込みであるといえます。令和9年4月予定の改正は、登録支援機関の「質」を一層問う内容となっており、名義貸しのような形での登録や、形だけの支援体制では今後は通用しなくなります。
これから登録を検討されている方はもちろん、すでに登録済みの支援機関においても、自社の支援体制が法改正後の基準を満たせるか、今のうちから点検と準備を進めておくことが不可欠です。
JAPAN行政書士法人では、登録支援機関の要件確認に基づく登録申請から、講習修了のサポート、支援体制整備に向けたコンサルティングまで幅広く対応しております。制度改正に乗り遅れないためにも、ぜひ一度お気軽にご相談ください。