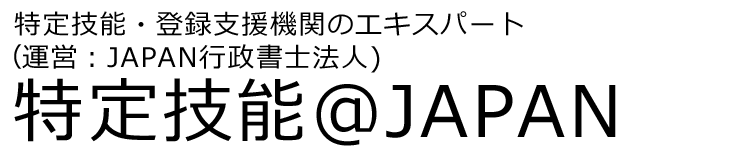まず、自動車運送業分野は2025年4月に運用が開始された最も新しい分野となります。そのため現在(2025年7月)においては入管としても未だ対応が追いついていない部分もあり、他の分野とは異なる自動車運送業分野特有の運用もあるため、事前の情報収集が非常に重要となります。一方で、新制度のため情報収集が難しいという面もあり、特定技能分野の中でも非常に手続きのハードルが高い分野であるといえます。今回は特に注意が必要な特定活動55号(自動車運送業分野で特定技能1号になるための特定活動)について触れていきたいと思います。
JAPAN行政書士法人では、既に当該分野において何人もの在留手続きをサポートした実績があるため、実例等を踏まえた詳しい手続きを解説してまいります。
原則特定活動(55号)を経る必要がある
通常、特定技能へ移行するためには試験の合格や技能実習の良好修了が必要となりますが、当該分野においてはそれに加え、日本で有効な運転免許の取得(外免切り替えを含む)や初任者研修の終了(バス・タクシー)が要件となっているため、その要件を満たすために特定活動を経ることが求められます。ただし既に日本の有効な運転免許を取得している場合は特定活動を経る必要がありません(海外からの呼び寄せの場合も同様)。
またこの点について、外国で既に大型免許を取得していたとしても、特定技能へ移行するための要件としては普通免許で十分であることから特定活動期間中に大型免許の外免切り替えを行うことは許されず、特定活動期間に一旦普通免許のみを切り替え、特定技能へ移行した後に大型免許の切り替えを行う必要があるので、雇用後大型免許を用いて就労するまでに、タイムラグが生じることにおいて注意が必要です。
オンライン申請ができない
現在ほとんどの在留資格においてオンライン申請が行えますが、この自動車運送業準備特定活動(特定活動55号)においては現状オンライン申請を行うことができません。そのため認定の場合には企業の所在地(外国人が従事することとなる事業余が異なる場合はその事業所の所在地)を管轄する入管窓口に提出しなければなりません。またオンライン申請では、申請人の署名などはデータで貰えば良かったものの、提出書類一覧表に「写し」と記載されていない書類に関しては原本が必要になり、送り出し機関を経由して申請人の署名入り書類を国際郵便で郵送してもらう必要がでてきます。
再度認定を受けて入国することは難しい
1度特定活動55号で認定を受けたものの、外免許切り替えに失敗し帰国せざるを得ないケースが発生することが予想されますが、この場合再び本特定活動で入国することができるかが問題となります。結論としましては、申請自体はできるものの、審査が厳しくなります。理由としてはそもそも在留期間の更新が許されていないため、簡単に2度、3度と認定を認めてしまうと事実上更新と変わらない結果となってしまうことが考えられます。しかしどの程度審査が厳しくなるかは審査内容に関わることから、入管からは明言されていません。
外免切り替え(日本の運転免許取得)を行う必要がある
この分野に特有の手続きとして外免切り替えがあります。一見単に外国の免許を日本で有効にするための単純な手続きのように思われますが、あらかじめ準備をしていないと想定外のことが起こる可能性があるため注意が必要です。まずこの外免切り替え手続きをするためには運転免許センターに予約をする必要がありますが、この予約を取るために地域によっては何ヶ月も待つことがある状況です。予約が取れたとしても試験の合格率が低く、受かるまで受験し続ける必要があります。そのため特定活動期間のまえに最寄りの運転免許センターの予約状況等を確認しておくことをお勧めいたします。
また特定活動期間は6ヶ月(トラック)又は1年(タクシー・バス)の在留期間が与えられますが、更新をすることができないため、この期間内に外免切り替えや初任者研修を行うことができなければ、特定技能として就労することができなくなってしまいます。これらの期間は十分なようにも思われますが、初めて外国人が日本に来る場合にはトラブルが起こることも珍しくはないため、特にトラック運送業において受け入れる場合にはスケジュール設定等に注意が必要です。
外免切り替え手続きが厳格化へ
外免切り替え手続きに関しては、観光ビザなどの短期滞在者がホテルなど宿泊先の住所で免許を取得できることや、交通ルールに関する知識確認の問題が簡単すぎることなどが問題視され、厳格化などを求める声が上がっていました。それを踏まえ、2025年10月1日運用開始予定の道改正路交通法施行規則では、外免切り替えの申請時に申請者の国籍にかかわらず、例外的な場合を除いて「住民票の写し」の提示が求められることとなりました。また住民票の写しがない場合は在留資格認定証明書などで代用することもできます。
この点に関して、中長期在留者にとっては大きな改正とはなりませんが、一方で簡単すぎることなどが指摘されていた外免切り替えにおける交通ルールに関する知識確認の問題に関しては、イラスト問題を廃止し、問題数を従来の10問から50問に増やし、審査基準に関しても現在の70%以上から新規免許取得時と同様の90%以上に変更されます。運転に必要な技能を確認する技能確認についても横断歩道や踏切の通過など課題を新たに追加し、審査基準に関しても合図の不履行や右左折方法違反などの採点を厳格化するということです。先述の通り、現状でも外免切り替え試験の合格率は低いのですが、改正後はより低くなることが予想され、在留資格取得の前提として無視できないハードルとなる可能性もあります。
そのため、申請人に対してあらかじめ外免切り替えに向けた試験の勉強をしてもらうなどの準備が必要となるといえます。
従事可能な業務内容
特定活動55号は日本における免許を取得したりするための在留資格であり、運送業務を行うことが想定されているわけではありません。そのため、本特定活動期間中は運送業務に従事することは許されず、それに付随する業務(車両清掃等)のみを行うこととなる点に注意が必要です。そのため、特定技能1号に移行するまでの期間中に行うことができる業務をあらかじめ用意することが重要となります。
この点に関し例えば、A社にて特定技能外国人を雇うことを予定しているもののドライバー業務以外を用意できない場合、グループ会社Bで特定活動期間を経た後にA社で特定技能1号で雇用することは可能なのかが疑問となりますが、入管としては特定活動B社→特定技能A社は原則許されていないとのことなので注意が必要です。(なお自動車運送業以外の特定活動では特定活動B社→特定技能A社は許されています。)
まとめ
自動車運送業分野における特定技能外国人の受け入れは、他分野と比べても手続きが煩雑で、外免切り替えなど独自の要件も多く、慎重な対応が求められます。とくに本特定活動(55号)は、制度自体が新しく、かつ今後の制度改正の影響も大きく受ける分野であるため、常に最新の情報に基づいた適切な準備と計画が不可欠です。
JAPAN行政書士法人では、これまでに複数の申請実績を通じて得た現場の知見とノウハウをもとに、単なる書類作成にとどまらず、採用計画の立案から在留資格の取得、就労開始後の運用支援まで、ワンストップで対応しています。
「外国人材の受け入れは初めてで不安が多い」「外免切り替えのスケジュール管理が難しい」といった企業様のお悩みにも丁寧に寄り添い、実現可能な受け入れ体制づくりをサポートいたします。特定技能外国人の受け入れをご検討中の企業様は、ぜひ一度、当法人までお気軽にご相談ください。