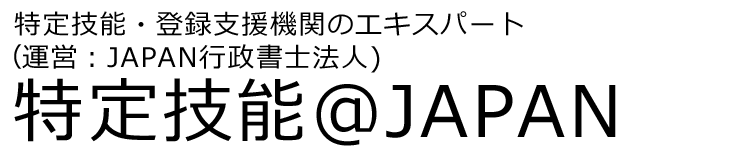育成就労制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されるとの発表がありましたが、施行日は現(2025年6月)時点では2027年4月となっています。本稿では、現段階で検討されている制度内容や、技能実習制度との比較を交え、育成就労制度について詳しく解説していきます。
施行までのスケジュール(予定)
・~2025年3月
基本方針決定(関係閣僚会議決定・閣議決定)
・2025年5月~2025年12月
分野別運用方針の作成(専門会議→有識者会議)
・2025年12月
分野別運用方針決定(関係閣僚会議決定・閣議決定)
・2026年~2027年4月(施行)
分野別運用方針決定(内容の変更や新分野の追加があれば随時)
事前申請(監理支援機関の許可等)
・2024年~2027年4月(施行)
送出国とMOCの交渉・作成・署名
※ 育成就労産業分野の設定は、必要に応じて、改正法施行までの間にも行われます。
技能実習に関する経過措置
基本的に、施行日前に入国し、施行日時点で現に技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習を行うことができますが、施行日前に入国していない場合でも、技能実習計画の認定の申請をしている場合は、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があります。この点に関しては、施行日から3か月以内に開始することを内容とする技能実習計画に限ります。また、施行日前に既に技能実習を終えて出国している場合は、技能実習生として再度入国することはできず、その後は育成就労外国人として入国することとなります。
つまり施行日以降に技能実習生として在留するためには、施行日前に技能実習計画を開始し又は申請する必要があり、既に技能実習を終え、帰国してしまっている場合は育成就労制度での入国が求められることとなります。
育成就労制度の特徴(技能実習制度との比較)
技能実習制度から育成就労制度に変わるうえで、抑えておくべき点や注意すべき点を解説いたします。
制度目的
育成就労制度は、「育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする」とされています。技能実習制度では、就労を通じて技能を修得させることが目的という建前でしたが、実際には日本における労働力不足の補填として使われており、現実的にも労働力不足に対応する必要性があることから、「人材を確保することを目的」とした新制度が創設されました。中身としては技能実習と大きく異なる制度ではありませんが、他国への技能移転を目的とした制度から、国内の労働力不足の解消のために制度に改正されており、目的は大きく異なる制度であるといえます。
本人意向転籍
技能実習制度においては、実習先の就労環境が劣悪な場合など、やむを得ない場合でなければ原則転職は認められていませんでしたが、育成就労制度においては、外国人本人に対する人権にも配慮し、一定の条件のもとに本人の意向による転籍が認められることとなりました。また令和7年2月13日に行われた特定技能制度及び育成就労制度の運用に向けた有識者懇談会が設けられ、転籍の要件について議論されました。現在未だ確定には至っていませんが、いくつかの論点が挙げられており、暫定的な案もありますので紹介させていただきます。
本人意向転籍の要件の検討の方向性
まず転籍の要件を検討するうえで、転籍後も育成が円滑に行われるようにする必要があり、また過度な引き抜きや本人意向による転籍者の都市部への集中を防止する必要があるとされています。この2つの前提のもと、大きく分けて以下の4つの論点が議論されています。
論点①
育成就労制度は、長期的な人材確保のため、特定技能1号レベルの技能を習得させることを目的としており、適切な「育成」環境が求められるところ、育成就労評価試験の合格率などを考慮して優良なもの(転籍先)に限るべきか。
💡現時点での検討内容①
本人意向による転籍先を、試験合格率や育成体制、法令遵守状況等の基準を満たす優良な受入れ機関に限ってはどうか。
論点②
転職者ばかりを採用する企業が現れると「育成」が適切に行われない懸念があるため、他の受入れ機関からの転籍者の割合についてどのように考えるか。
💡現時点での検討内容
受入れ機関に在籍する育成就労外国人に占める本人意向による転籍者の割合を、1/3以下としてはどうか。
論点③
地方の人材不足の深刻化に鑑み、転籍者が都市部の受入れ機関に過度に集中することを防止するためにどのような方策が考えられるか。
💡現時点での検討内容
都市部の受入れ機関が都市部以外の受入れ機関から受け入れることができる転籍者数を、都市部以外の受入れ機関が受け入れることができる転籍者数の上限の1/2以下としてはどうか。
論点④
民間職業紹介事業者の関与を認めると、過度に転籍を勧める可能性があるため、非営利的かつ公正な第三者的立場の機関に関与させるべきところ、どのようにして民間職業紹介事業者が転籍手続に関与しないようにするか。
💡現時点での検討内容
育成就労計画の認定要件として、監理支援機関、外国人育成就労機構又はハローワーク若しくは地方運輸局以外からの育成就労外国人に係る職業紹介を認めないこととしてはどうか。転籍後の育成就労計画の添付書類において、転籍に係る職業紹介の主体を記載させることを想定。
以上が現在議論されている論点とそれに対する対応策となり、未確定の段階ではありますが、まずは方向性や考え方を理解できたのではないでしょうか。
転籍時における初期費用補填の仕組みの検討の方向性について
外国人を海外からしょうへいする際、職業紹介費、送出機関への送出手数料、入国後講習費などの多額の初期費用を負担して育成就労外国人を受け入れることとなります。一方国内にいる外国人を転職という形で雇用する場合、主にかかる費用としては職業紹介費くらいとなり、既に経験を積んだ外国人を少ない費用で雇用できることとなり不公平が生じます。結果企業としては転職で雇う方が有利になり、「育成」という趣旨とは反対の制度設計となってしまいます。
そこで本人の意向により転籍する場合、転籍後の受入れ機関がこの初期費用の一部を分担する仕組みが必要となります。また、転籍元と転籍先が補填すべき初期費用の額を交渉することとすると、双方にとって負担となり、また、育成就労外国人にとっては転籍の妨げとなる恐れがあるため、転籍元が負担した初期費用の一部について正当な補填を受けられるようにするとともに、補填すべき初期費用の額を巡るトラブルを防止するためのルールを設けることが検討されています。この前提のもと、大きく分けて以下の3つの論点が議論されています。
論点①
転籍の際に転籍先が支払うべき初期費用として一律の標準(固定)額(いわゆる有形コスト)を定めるとした場合、どのような費用を標準額として評価すべきか。
💡現時点での検討内容
受入れに必要な費用のうち、職業紹介費、入国前後の講習費、来日渡航費等が初期費用に当たると考え、これらの総額を一律の標準(固定)額として評価することとしてはどうか。初期費用のうち、例えば、来日渡航費及び送出管理費の一部に限っては、実費を勘案して初期費用に含めることとしてはどうか。
論点②
金銭による負担ではない初期の育成コスト(いわゆる無形コスト)をどのように評価すべきか。
💡現時点での検討内容
客観的把握が困難であるため、例えば、一律で標準額と同額の無形コストがかかっていると評価してはどうか。
論点③
転籍先が補填すべき初期費用について、外国人が在籍した期間に応じて按分することとした場合、その際の按分割合をどのようにするべきか。
💡現時点での検討内容
外国人の生産性(技能)向上に鑑み、例えば、按分割合を一律1年目:2年目:3年目=1:2:3と傾斜をつけて設定してはどうか。この場合、転籍先は、1年で転籍した場合には初期費用の5/6を、2年で転籍した場合には3/6=1/2を補填することになる。その上で、このように計算された補填額を、転籍先が転籍元に支払うことを約束すれば転籍可能としてはどうか。
- ~③のとおりとした場合の補填額の計算(金額は飽くまで一例)
初期費用が100万円の場合(転籍先の企業が補填する額)
1年で転籍:5/6(83万円)
2年で転籍:1/2(50万円)
特定技能制度との関係
特定技能制度に関しては、廃止こそされないものの、「適正化」したうえで存続という方針がとられています。実はこの「適正化」によって大きく変わる可能性もあり、外国人雇用に携わる方にとっては現段階から内容を把握していく必要があります。また特定技能へ移行するにあたり、育成就労制度を経由するインセンティブを増やし、一連の制度としての構築を目指しているものと伺えます。つまり、育成就労制度と特定技能制度を一体として理解する必要があるといえます。
特定技能1号に付与する在留資格の期間
現行制度においては、1年を超えない範囲の期間が付与され、少なくとも1年に1回は更新をする必要があります。しかし特定技能外国人の在留者数の増加に伴い見直されてきています。検討案では、例えば育成就労経験3年を経た外国人であれば、日本での在留、就労についての経験を踏まえ、在留期間の伸長を認めるというものもあり、期間によってはほとんどの外国人が育成就労を経ることになるのではないでしょうか。
従事可能な業務区分
現行制度下においては、技能実習生が従事することのできる業務区分と、特定技能外国人が従事することのできる業務区分が異なっています。例えば、物流経作業(倉庫におけるピッキングなど)においては技能実習1号で従事することができますが(技能実習1号においては従事可能な作業に制限がない)、特定技能の対象分野には含まれていません。またその逆のパターンも存在します。そのため、技能実習を修了後継続して就労できないケースもあり、外国人、受入企業双方にとって利益が少ないという制度的一面もありました。一方で、育成就労制度においては特定技能への移行を前提としているため、基本的に分野や作業可能な業務区分は同一になります。しかし本邦で育成を行うことが適切ではない一部の分野(現時点では、自動車運送業分野・航空分野)に関しては育成就労制度の対象外となるので注意が必要ですが、少なくとも育成就労修了後、特定技能に移行できない分野や業務区分は存在しなくなります。
制度移行への備えと今後の対応について
JAPAN行政書士法人
育成就労制度の創設は、これまでの技能実習制度の課題を正面から見直し、より実態に即した人材確保と人材育成の両立を目指すものです。本人意向による転籍の容認や初期費用補填制度の導入など、新たなルールの整備は受入れ企業にとっても重要な制度変更であり、早期に情報を収集し、社内体制を整えていくことが求められます。
現時点(2025年6月)では、制度の詳細は検討段階にあり、今後さらに制度設計や運用方針が具体化されていく予定です。技能実習制度からの移行や、経過措置に関する実務対応についても、移行期においては慎重かつ的確な対応が必要です。
JAPAN行政書士法人では、今後の制度変更に関する最新情報の提供はもちろん、受入れ企業様に対する個別の制度対応支援、各種申請業務、書類作成等を一貫してサポートいたします。制度移行に関するご不明点やご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
外国人材の受入れが「育成」と「定着」の両面で企業の力となるよう、法的専門家として引き続き実務の現場を支援してまいります。