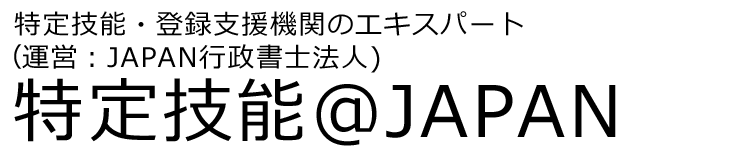2025年4月1日、特定技能1号の対象分野に自動車運送業が追加されました。具体的には、トラック運転手・タクシー運転手・バス運転手の3つの業務区分に分けられています。本稿では、それぞれの要件や従事できる業務内容など、自動車運送業において、特定技能外国人を雇用するうえでの注意点を解説します。
「トラック運転手・タクシー運転手・バス運転手」
それぞれの要件
まず、特定技能1号を取得するうえでの要件を説明するに当たり、1. トラック運送業(貨物運送業)2. タクシー運送業及びバス運送業(旅客運送業)の2つに分けることができます。以下にそれぞれの要件をまとめました。
1. トラック運送業
●技能水準を証するもの
・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)の合格証明書の写し
・第一種運転免許
●日本語能力を証するものとして次のいずれか
・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し
・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
*ただし、職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、いずれの試験も免除されます。
2. タクシー運送業及びバス運送業
●技能水準を証するもの
・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)又は自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)の合格証明書の写し
・第二種運転免許
●日本語能力を証するものとして次のいずれか
・日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
● その他
・業界団体が作成した新任運転者研修の修了を証する書類
まず当然ながら、トラック運送業とタクシー運送業及びバス運送業において、取得すべき運転免許証の種別が異なります。
一方注意すべきは、求められる日本語能力が異なるという点です。接客業務が想定されるタクシー運送業及びバス運送業については、より高い日本語能力の水準が求められます。また、技能実習2号を良好に修了することで、N4の代わりにはなりますが、N3の代わりにはならないため、タクシー運送業及びバス運送業については常に日本語能力試験(N3)の合格が求められることとなります。加えて、タクシー運送業及びバス運送業においては、新任運転者研修の修了も要件の一つとなっており、事前に研修を済ませることが必須となっています。
所属機関(受け入れ企業)が求められる要件
そもそも自動運送業分野において特定技能外国人を受け入れるためには、日本標準産業分類のうち、道路旅客運送業・道路貨物運送業のいずれかを営む企業である必要があります。またそれらを営む企業の中でも、「運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者」又は、「貨物自動車運送事業安全性評価事業に基づく安全性優良事業所の認定を受けた事業所を有する者」である必要があります。そのため大前提として、以上のいずれも満たしている企業でなければ、この分野において特定技能外国人の雇用はできないこととなりますので注意が必要です。
自動車運送業分野の特徴・注意点
自動車運送業分野は現在(2025年6月)最も新しく創設された分野であり、他の分野とは異なる運用があるため注意が必要です。
特定活動(55号)を経る必要がある
自動車運送業分野において、特定技能を取得するには原則特定活動を経る必要があります。これは運転免許の取得や新任運転者研修の修了が要件となっている点に起因すると考えられます。本来ならば、分野別の試験(技能水準・日本語能力)や対象分野の技能実習の良好修了によって特定技能の在留資格を取得し、ないしは移行することができます。しかしこの分野では、日本において有効な「運転免許の取得」が必要となり、国内で新たに免許を取得するか、外国で取得した運転免許を切り替える、いわゆる「外免切り替え」の手続きが必要となります。またタクシー運送業及びバス運送業においては、新任運転者研修の修了も必要になるため、より長い特定活動期間(上限はトラック運送業については6月、タクシー運送業及びバス運送業については1年)が認められています。
この点当該特定活動期間は、特定技能1号の通算在留上限期間である5年間に含まれませんので、特定技能1号移行後から5年間の雇用を予定して採用することができます。
特定活動(55号)経由の例外
入管の運用要領では、本邦に在留している外国人(「留学」や「家族滞在」等の在留資格で在留している者)が、自動車運送業分野において特定技能1号として活動するために必要な我が国の運転免許を取得している場合(トラック運送業に限る)、又は当該運転免許を取得した後、資格外活動許可を取得した上で新任運転者研修を修了した場合(タクシー運送業及びバス運送業に限る)においては、本特定活動を経由することなく、特定技能1号へと移行することができる旨明記されています。
また、「留学」や「家族滞在」等の在留資格が例としてあげられていますが、入管の運用としては、他の就労系在留資格で本邦に在留している外国人も例外ではなく、既に日本の運転免許を取得していたり、新任運転者研修を修了していたりする場合には特定活動(55号)を経る必要がなく、直接特定技能への移行が可能となります。
運転免許取得(外面切り替え)の注意点
先ほど、運転免許取得のために原則特定活動(55号)を経る必要があると説明しましたが、特にトラック運送業で注意すべきなのが、この特定活動期間中に大・中型免許を取得することは認められていないという点です。あくまで、自動車運送業における特定技能1号の要件を満たすための期間であり、普通免許を取得すれば要件を満たすこととなるため、(特定活動の時点で、運転免許の取得や新任運転者研修以外の要件を満たす必要はあります)速やかに特定技能1号への移行を申請する必要があります。またそもそも、大・中型免許を取得するためには、普通免許等での運転歴が3・2年必要なため、ほとんどの場合で既に運転免許を取得している外国人を雇用することとなり、外面切り替えでの日本の免許取得がメインになると考えられます。この外免切り替えにより日本の免許を取得する場合でも、外免切り替え後、特定活動期間中に大・中型免許を取得することは許されず、既に外国の大型免許を取得している場合であっても、一旦普通免許のみを切り替え、特定技能移行後に大・中型免許を切り替えるという手続きを経ることになります。
トラック運送業においては、特定技能移行に必要な要件としての免許種別と、実際に就労するうえで必要な免許種別が異なる点に注意が必要です。
運転免許の取得費用の負担は誰がすべきか
運転免許の取得費用について、所属機関(受入企業)が負担することが望ましいとされています。しかし、外国人が十分に理解できる言語による説明を行うなど、丁寧な説明を心掛け、事前に受入れ外国人の了承を得るようにすることを条件に、外国人本人に負担してもらうことも許されています。
なおこの点に関し、外国人が一定期間勤務することを条件として、免許取得費用の返済を免除する内容の契約を締結することや、受入れ外国人が返済途中に退職した場合に、貸付金の残額を一括で返済する内容の契約を締結することは許されないので注意が必要です。しかし、所属機関が当該費用を賃金に含めて補填することは許されています。
作業可能な業務内容
まず大前提として、「特定技能1号相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事することが求められています。この点トラック運転者の業務区分については、運行業務(安全な貨物の輸送等)及び荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積付け等)が対象となります。つまり、貨物の積み入れから、その運送業務までが当分野で許可されている業務内容であり、専ら他の作業内容に従事することは認められないこととなります。とはいえ、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる「関連業務」に付随的に従事することは許されているため、上記の業務内容以外は全く行ってはいけないというわけではありません。
タクシー運転者及びバス運転者の業務区分については、運行業務(安全な旅客の輸送等)及び接遇業務(乗客対応等)が対象となります。そのため、旅客の輸送やその対応が当分野で許可されている業務内容となりますが、先述の通り、「関連業務」に付随的に従事することは許されています。
従事させる業務が関連業務に含まれるかについては、一般的には車の清掃業務などが想定されますが、業務内容や他の日本人の労働状況等により個別具体的に検討する必要があります。そのため不明な点等がございましたら、JAPAN行政書士法人にお気軽にご相談いただければと思います。
最後に
「運転免許の取得手続きって複雑そう」「採用までに何を準備すれば…?」そうした疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。JAPAN行政書士法人では、特定技能外国人の受け入れに関する実務を多数支援しています。初回のご相談も丁寧に対応いたします。